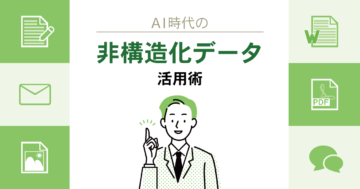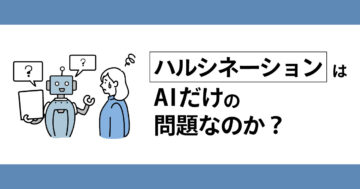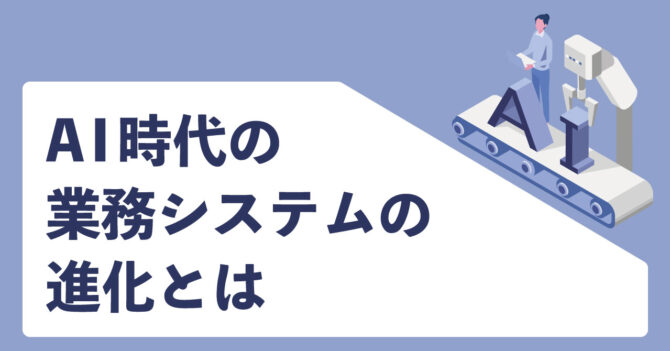
こんにちは。ワークスアイディの奥西です。
かつては紙ベースで行っていた業務も、今ではPCやタブレット上での作業が当たり前になりました。
WordやExcelといったオフィス系ツールはもちろん、業務を効率化するための社内システムも各社で導入が進んでいます。
その一方で、「ツールやシステムを入れれば業務が劇的に改善される」という単純な話ではなくなってきたとも感じます。
特に最近では、プログラミングが必要な汎用言語でのシステム開発に加え、
ローコード・ノーコードツールの活用や、業務部門自らがアプリケーションを作成する「市民開発」といった動きも出てきています。
このような流れの中で、AI時代のシステムはどうなっていくのか?そんな「問い」が浮かんできました。
そこで今回は
皆さまと一緒に考えていきましょう。
色んな意見がある「問い」の為、
皆さまのそれぞれの考えの参考までにご覧ください。
個別のカスタマイズ開発はどうなるのか!?
■個別カスタマイズ開発の課題
こうした声が、今も現場から頻繁に聞こえてきます。
経営陣は「業務の効率化」や「全社の標準化」「データ活用の基盤づくり」を目的にDXを推進しようとしますが、
いざ、プロジェクトが始まると現場からの細かな要望や従来業務の踏襲が優先され、
結果として個別対応やカスタマイズ開発が増えていく…。
こうした経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実際、経済産業省の「DXレポート」2025年の崖でも、
こうした過剰なカスタマイズがシステムを複雑化・ブラックボックス化させ、将来的な足かせになると指摘されています。
また、パッケージ導入にもかかわらず、追加開発が繰り返されることで
もちろん、現場目線のUI/UXや使いやすさは非常に重要だと感じています。
現場に寄り添うことは、システムの定着にもつながる大切な要素です。
但し、
全社横断的なデータ活用や業務の横断的な改革を阻む原因にもなっている
日本は「個別最適」、アメリカは「全体最適」
一方、グローバルな視点で見ると、
米国の先進企業の多くは「現場の個別最適」よりも
実際に公表されているデータを見てみると、
・日本:システム開発投資の約7割がカスタマイズに費やされている
・米国:パッケージ導入・クラウド活用が主流で、カスタマイズ比率は2~3割程度
つまり日本では
米国では
特に、人材の流動性が高い環境では、業務を人に依存させない標準化の重要性が高まるのです。
これからの設計思想
個別開発はプロジェクト初期において「現場に寄り添った設計」として評価されがちです。
しかし現実には、要件追加・仕様変更・既存システムとの連携対応などが相次ぎ、
当初の1.5倍以上の費用や期間がかかるケースもあります。
結果としてIT予算の多くが「維持管理コスト」や「レガシー対応」に費やされ、新しい取り組みに余力がなくなる。
これではDXどころではありません。
これからのAI時代、システムに求められるのは「現場の業務をそのままシステム化する」ことではなく、
もちろん、UI/UXのわかりやすさや現場にとっての使いやすさは引き続き重要です。
しかしそれは、「個別対応」ではなく「全体最適化された仕組みの中で実現する工夫」として、設計されるべきではないでしょうか。
システムは「記憶」から「活用」へ
AI時代のシステムには、もう一つ大きな転換点があります。
それは、
従来のシステムは、業務プロセスをITで記録・保存することが主な目的でした。
たとえば営業日報や作業報告なども、「実績を残す」ための仕組みとして機能していました。
しかし、これからの時代に求められているのは
たとえば、営業活動のデータを蓄積するだけでなく、
「どの顧客に、いつ、どのようなアクションを取るべきか?」
といった示唆を得るための活用基盤として、システムが進化する必要があります。
まさに、AIが得意とする領域です。
しかしここでも課題となるのが、
現場に合わせた個別システムを積み重ねてきた結果、
「データが分断され、全社横断の活用ができない」という壁に、多くの企業が直面しています。
ある商社では、営業部門ごとに別々のシステムを開発・運用していました。
一見すると、現場に最適化されており運用上の問題はなかったのですが、
全社でデータを集計・分析しようとした途端、定義やフォーマットの違いが障壁となり、
横断的な分析ができない、という相談を受けたことがあります。
これは決して特殊な事例ではありません。
部門に最適化されてきた背景から、多くの企業で現実に起きている課題でもありますよね。
生成AI時代、システムに求められる役割とは
ここまで、「個別最適」から「全体最適」へ、そして「記録」から「活用」へと、
システムの役割が大きく変わってきている流れをご紹介してきました。
では、生成AIの活用が前提となる時代には、システムはどのように進化していくべきなのでしょうか。
キーワードは
これからの業務設計やシステム設計では、
AIがやるべきこと、人が担うべきことを明確に切り分け、
要するに、AIを前提としたビジネスプロセスの設計です。
いくつか進化のポイントを洗い出してみますね。
(1)ルールベースから「柔軟な対応」へ
従来は定型業務やルールベースの処理を自動化することが主流でしたが、
生成AIは、文脈を理解して「状況に応じた判断」や「例外処理」にも対応できます。
たとえば、問い合わせ対応のチャットボットが、想定外の質問にも回答し、必要に応じて選択肢を提示する、といった柔軟な対応が可能になります。
(2) 部門最適から“全体最適・学習型”のシステムへ
AIチャットボットや業務支援エージェントが、複数の部門にまたがって業務を横断的にサポート。
日々の業務データから最適なプロセスを自動で学習・改善していく進化するプラットフォームとなります。
構造化データだけでなく、メールや議事録などの非構造化データも対象になることで、企業内データの価値が飛躍的に高まります。
(3) 入力作業からの解放——自動化と要約による効率化
ナレッジや業務ログからAIが必要情報を抽出・要約し、
現場の入力負担を大幅に削減します。
システムそのものに音声AIなどを活用していく未来も近いでしょう。
(4) 経営と現場をつなぐ“意思決定の翻訳者”としてのAI
生成AIは、現場の改善提案を吸い上げ、経営視点で整理・要約することも可能です。
また、経営陣の方針や判断を、業務フローに即した形で現場に落とし込む橋渡し役にもなります。
AIがトップダウンとボトムアップを日常的に接続する存在になるイメージです。
(5)知識の伝承やベテラン技術の標準化
属人化しがちなノウハウやベテランの判断パターンも、AIが観察・学習することで、
新人でもすぐに活用できる状態に。
AIが社内で最も詳しい存在になっていくイメージです。
組織のナレッジが失われない仕組みとして、AIが中核を担うようになります。
こうした進化によって、
AI時代のAIシステムは変化していくと考えます。
AIエージェントも組み込まれていくと、
データの抽出や加工、分析がもっと容易になっていきます。
従来は「業務に合わせてシステムを変える」か「システムに合わせて業務を我慢する」しか選択肢がありませんでした。
しかし生成AIによって、
まとめ
AI時代のシステム開発では、
これまでのような「現場の個別最適」を積み重ねるのではなく、
全社横断での業務標準化やデータ活用を見据えた
従来のように記録を残すだけの仕組みではなく、
データを活かし、
AI時代のシステムは、人とAIの協働を前提とし、
属人化の排除・ナレッジの共有・業務自動化・経営と現場をつなぐ基盤として、
企業全体のパフォーマンスを最大化するプラットフォームへと進化していくでしょう。
是非、皆さまの会社でも「AI時代のシステムについて」
議論してみてください。
本日もGOOD JOB!!
▼こちらもおすすめ