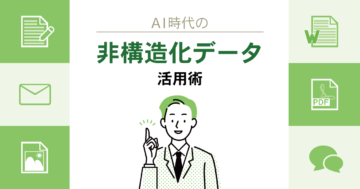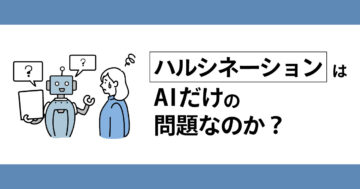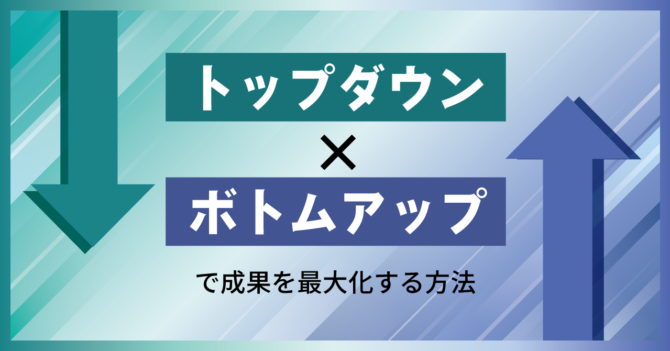
こんにちは、ワークスアイディの奥西です。
これまで個人の業務効率化としてのAI活用が中心でしたが、
いま企業は本格的に“組織としてのAI活用”へ舵を切りはじめています。
おかげさまで私も、さまざまな企業のAIプロジェクトを並走支援する機会が増え、
部署横断で進める面白さと難しさの両方を実感しています。
👻よくあるつまずきエピソード
「AIで何かできないか?」
ある会議での上層部の一言を起点に、
DX推進室・情報システム部・現場が動き出す。数カ月後に起こりがちな結末は…
- PoC(実証実験)は実施したが成果が見えない
- 誰の課題を解決していたのかわからない
このギャップは多くの企業で共通しています。
今回は、AI活用を始める企業が必ず直面する
『技術アプローチ(トップダウン)』と『課題アプローチ(ボトムアップ)』の
2つの進め方について、現場のエピソードを交えながら整理します。
どちらが正解かという話ではなく、
技術アプローチ(トップダウン)の強みと落とし穴
「AIで何ができるか?」という
生成AI、画像認識、需要予測など最新技術を起点に、競争優位の芽を探ります。
📌メリット
- 最新技術をいち早く試し、競合優位性を確保しやすい
- 経営層の関与が強く、意思決定が速い
- 社内外の注目を集め、変革のムードを醸成できる
📌デメリット
- 現場課題との接点が弱く、成果が曖昧になりやすい
- 導入自体が目的化し、定着しにくい
- 利用部門の納得感を得にくく、利用率が伸びない
例えば[生成AIで議事録要約を自動化]というPoCです。
精度は高いのに、現場では使われていない…。
理由を聞くとこのような声がありました。
- 別のツールで代替済み
- 使い方が浸透していない
- 業務フローに組み込まれていない
技術は優れていても、利用文脈が欠けると定着しない。
とはいえ、
鍵は「効果が最大化される文脈」を設計できるかどうかです。
課題アプローチ(ボトムアップ)の強みと限界
「どの業務・ビジネス課題を解決するか?」を起点に、
実装フェーズでは特に重要です。
📌メリット
- 現場ニーズに直結し、実運用・定着につながりやすい
- 小さな成功体験を積み重ねやすい
- 関係者の理解と協力を得やすい
📌デメリット
- 技術理解が浅いと解決策が限定されやすい
- 「AIでなくExcelで十分」という判断に落ち着きがち
- 現場起点ゆえに全社展開が難航することがある
例えば製造業での[歩留まり率改善]をテーマとした課題アプローチ。
現場は「AIは難しい」「データが足りない」と考え課題に蓋をしていましたが、
実際はデータを少し整えるだけで異常検知が可能なレベル。
往復設計が成果を生む。鍵は「翻訳者(トランスレーター)」
AI活用は、“技術起点”か“課題起点”かの
トップダウンの推進力と、ボトムアップの実装力。それらを橋渡しする
ご支援先では、[AI推進チーム(技術)]と[業務課題チーム(現場)]を
別々に立ち上げ、後に合流してワークショップを実施。
経営層が『技術の可能性』を示し、現場が『実際の課題』を提示することで、
特定のツールに縛られず、当初想定以上の副産物が生まれました。
重要なのは、
🚩実践ステップ:課題×技術の往復運動
- 現場ヒアリングで“解決すべき課題”を言語化する
- 課題に適した技術候補を選び、スモールスタートで検証する
- 検証の定量・定性結果をもとに、経営へ“次の一手(投資と展開)”を提案する
- 成果が出た業務設計を標準化し、対象部門を拡大する
- この往復を繰り返し、組織としての“AI活用軸(何に効かせるか)”を定義する
ポイントは、
- 「AIの可能性をビジネスの言葉で語る」こと
- 「現場課題の本質を捉え、再現可能な形で言語化する」こと
結局は、『技術アプローチ』と『課題アプローチ』の両輪でビジネスを進化させていくことが
重要な視点とも言えますね。
まとめ
AIは単なる自動化ツールではなく、
課題の整理や理想の再設計を促す“きっかけ”にもなっています。
技術と課題、経営と現場の
テクノロジーと課題解決の両輪を意識し、同じ地図を描けるチームづくりを進めていきましょう。
皆さまの会社でも、ぜひ『AIプロジェクトの進め方』について議論してみてください。
トップダウンとボトムアップを往復する設計が、成果への最短ルートです。
それでは、本日もGOOD JOB!!
▼こちらもおすすめ
 AI時代の業務プロセス設計とは? – 業務の主役が“人”から“AI”へと変わるとき –
AI時代の業務プロセス設計とは? – 業務の主役が“人”から“AI”へと変わるとき –AI時代に求められる業務システムの変革と、全社横断でのデータ活用を実現するための考え方をわかりやすく紹介します。