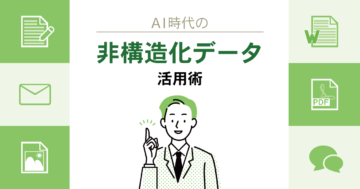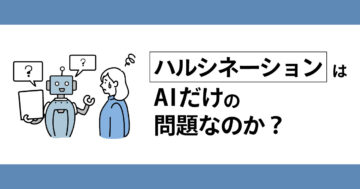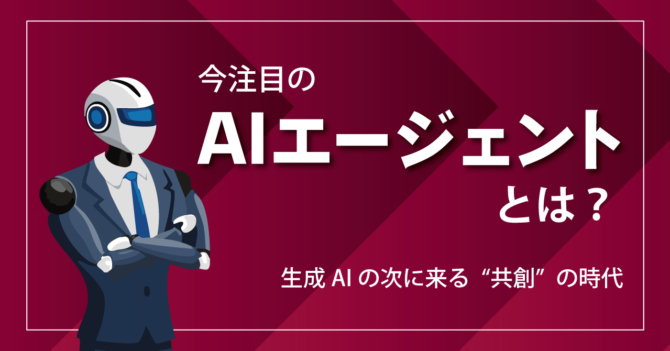
こんにちは。ワークスアイディの奥西です。
AIに関するニュースやサービスは、日々アップデートされ、各社の進化と競争のスピードには目を見張るものがあります。
AIは産業革命を起こすインパクトがあり、今後5年、10年の間に「仕事の在り方」が大きく変わる可能性を秘めています。
とはいえ、AIを導入した企業すべてが「業務が大きく変わった」と実感しているわけではありません。
実際には、
そのような中、注目を集めているのが
今回は、この「AIエージェント」とは何か、そして何ができるのかについて、わかりやすく解説していきます。
【お知らせ】
AIエージェントについてさらに詳しく知りたい方へ向けて、無料ウェビナーを開催します。
こちらも是非ご参加ください。
AIエージェントとは?
従来の「AIツール」や「対話型のチャットボット」は、あらかじめ決められたルールや手順に沿って動作する、
たとえば、問い合わせ対応や定型的なレポート作成、定まったルールに基づく業務などです。
それに対して「AIエージェント」は、必要に応じて外部情報をリサーチし、状況に応じて最適なアクションを選択し、さらにその行動結果を「記憶」することができます。
要するに
目標に向かって「自分で考え、調べ、動く」AIだと捉えてください。
AIエージェントの先駆けとされるのは、2023年の「Auto GPT」だと言われています。
以降、言語モデルの進化とともに技術は急速に進化し、2025年には「AIエージェント元年」と言われる様になりました。
皆さまの業務の中でも、定型的なルールベースの仕事、非定型的で情報や状況に応じて判断する仕事など、様々な種類のタスクがありますよね。
定型的なルールベースの仕事であれば、これまで通り、生成AIやRPAでも対応可能ですが、
非定型で柔軟な対応が必要な仕事では、AIエージェントの活躍の場が広がっています。
こんなAIワーカーが社内にいるだけでも、きっと日々の業務が大きく変わるはずです。
AIエージェントの「4つの役割」
実際に、AIエージェントが「自分で考え、動く」ためには、どのような要素が必要なのでしょうか。
ここでは、AIエージェントを構成する4つの基本的な役割をご紹介します。
1.役割(ペルソナ・タスク)
まずAIエージェントには、
市場調査を担う「リサーチャー」や、スケジュールや情報整理をこなす「秘書」、見込み顧客に提案を行う「営業アシスタント」など、
目的に応じたペルソナを与えることで、AIエージェントは
2.思考(Chain of Thought)
AIエージェントの特長のひとつが、
Chain of Thought(思考の連鎖)と呼ばれる手法で、複数のステップを論理的に進め、
仮説を立て、根拠をもとに推論します。
これにより、「なぜその結論に至ったのか?」が説明できるAIとなります。
人間以上の情報量をもとに思考してくれるため、新しい視点や気づきを与えてくれることもあります。
3.行動(ReAct・Reflexion)
AIエージェントは、考えるだけではなく
代表的な行動モデルが、以下の2つです。
ReAct(Reason + Act):思考しながらアクションを実行し、実行結果を受けてさらに思考を深めるサイクル。
Reflexion(反省・再考):一度の失敗で終わらず、過去の行動を振り返り、必要に応じて戦略を修正するサイクル。
つまり「やりっぱなし」ではなく、
4.記憶
そして最後に、AIエージェントは
過去のやりとりや成果を記憶し、それをもとに次の判断や提案に活かすことが可能です。
例えば
「A社には以前こういう提案をして好反応だった」
「過去に失敗した手法は避けよう」
といったナレッジを活かして、より精度の高いアウトプットが生まれます。
さらに、ユーザーごとの履歴や嗜好を反映して提案を変える
AIエージェントと生成AIの違いとは?
ここで「生成AI」と「AIエージェント」のその違いを整理しましょう。
生成AI:プロンプトに従う“受動的アシスタント”
生成AI(ChatGPT、Claude、Geminiなど)は、
ユーザーの指示(プロンプト)に従って、テキスト・画像・音声などのコンテンツを
たとえば、「今週の市場トレンドを要約して」と指示すれば、即座にまとめを返してくれる「優秀なアシスタント」です。
社内のドキュメントやナレッジを連携させれば、業務に即した回答が可能なAIアシスタント(RAG活用型)としても活用できます。
ただし、基本的には受け身の応答にとどまり、ユーザーの操作や指示があって初めて動き出す点が特徴です。
AIエージェント:自ら動く“能動的ワーカー”
一方、AIエージェントは生成AIの能力をベースにしつつ、
たとえば、マーケティング担当者の「今週のトレンド調査をお願い」といったざっくりした依頼にも、
- 必要な情報源を自ら選定
- 収集・分析
- 必要に応じて仮説を立てる
- 結果をレポーティング
…という一連の流れを「自律的」に遂行する力を持ちます。
つまり、単なる情報生成を超えて、
今後はAIエージェントが、カスタマーサポートや問い合わせ対応の自動化、
営業やマーケティングのリサーチ、データ分析の意思決定支援などの分野で、
高度に幅広く、能動的に対応してくれる様になっていきます。
このように、
能動的に業務を遂行するAIエージェント
という違いを理解することが、今後のAI導入を進める上でのカギになります。
今後、企業での活用においては、業務のユースケースに応じて、
生成AIやRAGを活用したAIアシスタントと、プロセス全体を担うAIエージェントをどう使い分けるが、
AI活用を推進するリーダー・マネジメント層に求められる視点だと言えるでしょう。
AIエージェント時代に求められるスキル・マインドセット
AIエージェントが組織にもたらす変化は、単なる「業務効率化」だけではありません。
本質的には、
これまでご紹介してきたように、AIエージェントは自律的に動き、複雑な業務にも対応できる存在です。
とはいえ現時点では、人とAIが互いに補い合いながら協働することが、最も効果を発揮する形だと考えられています。
では、人間はAIエージェントとどう向き合い、どのようなスキルやマインドを持つべきなのでしょうか?
ここでは、AIエージェントと共に働くうえで重要になる「3つの力」をご紹介します。
①問いを立てる力
AIエージェントは非常に賢い存在ですが、何をすべきかをゼロから考えてくれるわけではありません。
AIエージェントを使いこなすためには、
どんなことを調べるべきか?どんな仮説を検証したいか?という
これは、業務におけるボトルネックの発見にもつながる重要な視点です。
AIにうまく仕事をしてもらうには、まず
②フィードバックを与える力
AIエージェントは「使いっぱなし」では育ちません。
期待とズレた成果が出たときこそ、「なぜその答えになったのか?」をAIに問いかけ、
プロセスを可視化することで、AIの精度は徐々に高まっていきます。
③人間らしい共感や倫理観
最後に必要なのは、
どこまでをAIに任せ、どこから人が関与するか。
AIエージェントの提案や結論を鵜呑みにせず、その判断は現場で通用するか?
社会的・倫理的に受け入れられる判断か?といった「共感」や「倫理観」は、人間にしか担えません。
どこまでをAIに任せ、どこから人が関与すべきか。
この
まとめ
AIアシスタントやAIエージェントが、企業の現場に本格的に浸透し始めています。
こうした変化の中で最も重要なのは、
社内ドキュメントを連携させ、質問に答える「AIアシスタント」として活用するだけでも、
業務効率や情報共有の面で大きな変化を感じられるはずです。
また「AIエージェント」についてもいきなり全社導入を目指すのではなく、まずは
「どんな業務なら任せられそうか?」
「どの部門で最初に試せそうか?」
そんな問いから、社内で議論をスタートしてみてはいかがでしょうか。
是非、皆さまの会社でも「AIエージェント」について議論してみてください。
それでは本日もGOOD JOB!!
▼こちらもおすすめ